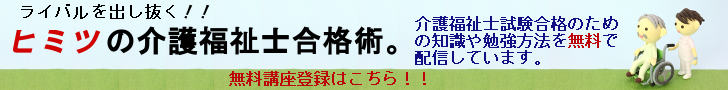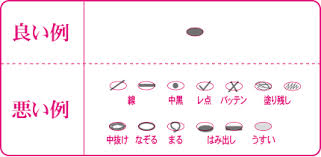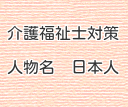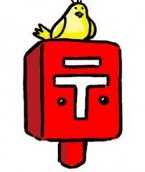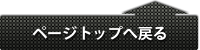8、発達と老化の理解 介護福祉士試験 ポイント

にほんブログ村
ぽちっとお願いします!!
今回は、発達と老化の理解です。
生活不活発病(廃用症候群=高齢者に起きやすい
機能を使わない状態が長く続いたために機能が
低下するものである。
筋力低下、関節の拘縮、骨粗鬆症、起立性低血圧、
認知症の進行などさまざまな症状があり、
全身の機能が低下しやすい高齢者は進行が早い。
関節リウマチ=朝の手足のこわばりが特徴
原因不明の疾患である。骨破壊が進み、関節の変形、
炎症を繰り返す。症状としては、朝に見られる手足の
こわばりが特徴で、寒さや低気圧、精神的ストレス
などで悪化する。関節・筋の拘縮の予防・改善には
関節可動域運動を行う。
自己受容=自分の弱点も含めて受け入れること
自分の長所だけを見つけてよしと
することではなく、自分の欠点や弱点
も含めて、自分自身を受け入れることである。
見当識障害がある高齢者 日付などを繰り返し
聞かない見当識障害は、日付や時間、自分がいる
場所などがわからなくなる障害である。
日付などを教え込もうとして繰り返し聞くと、
見当識障害のある高齢者にとってかなり強い
ストレスになる場合があるので注意が必要である。
老化の個人差=老年期に拡大する
老化がどのような現れ方をするかは、
遺伝的要因、生活習慣などの生き方の相違に
よるところが大きい。
感覚の鈍化=老年期には視覚、味覚、皮膚感覚など
感受性が低下する。これは、老化現象である。
例えば、味覚については、味覚の受容器官の
味蕾細胞が減少するため、味に関する感覚が鈍くなる。
高齢者のうつ状態=身体症状として現れることが多い
肩こり、腰痛、便秘、頭が重いなど身体的症状
として現れることが多い。
身体の症状の背後にうつ病が潜んでないか、
注意が必要である。
骨粗鬆症予防=カルシウム。たんぱく質、ビタミンD、Kの摂取
骨中のカルシウムを出産のため
用いてしまっていること、女性ホルモン
減少の影響などから、骨の密度が低下しやすい。
骨の構成成分であるカルシウムの摂取と、
その吸収を促す良質なたんぱく質、
ビタミンD・Kの摂取が必要である。
また適度な運動も効果がある。
前立腺肥大症の進行=尿閉になりやすい
頻尿になる、尿が出にくい、残尿感がある、
尿が出ないなどの症状が現れる。
この尿が出ない状態を尿閉という。
また、尿が少しづつ漏れる溢流性尿失禁も生じやすい。
高齢者の感染症=呼吸器系と尿路系の感染が多い
などの呼吸器系感染症と、膀胱炎などの
尿路感染症である。
高齢者は、免疫力が低下しているために
感染しやすい。また、尿路感染の場合は
留置カテーテルを使用することが原因の1つとなっている。
C型肝炎ウイルス=肝がんの発生に関係
そのまま治療がなされないと、
肝がんに進行する可能性がある。
脳内出血=大脳基底核部によく起きる
調節するなどの働きをしており、
脳内出血をすると出血側と反対側の
半身麻痺が生じることもある。
咳反射=低下すると、誤嚥を起こしやすい
その異物を排出するために激しく咳き込むことをいう。
高齢者では、この咳反射の機能が低下しているため、
誤嚥や誤嚥性肺炎が起こりやすい。
温かい食事、冷たい食事、辛い食事は、
咳反射・嚥げ下反射を高める効果がある。
また、口腔ケアの定期的な実施によって、
咳反射や嚥下反射の維持・改善につながる。
空の巣症候群=初老期に起きやすい
独立するときなどに親(特に母親)
が陥る虚脱状態である。
役割喪失感から、うつ状態になったり
アルコール依存症になったりしやすい。
糖尿病患者=過食に気をつける
の取りすぎを避けること、栄養のバランスを
とってカロリー摂取量を守ることが大切である。
また、1日に20~30種類の食品をとるとよい。
尿失禁=水分制限をしてはいけない
を控えようとしてしまいやすい。
しかし、水分制限をすると、脱水症になりやすく、
尿路感染症にもかかりやすくなるので、
水分制限をしてはいけない。
糖尿病=進行すると失明の危険
大きな割合を占めている。
糖尿病の患者については、医療関係者と連携し、
血糖値のコントロール、定期的な眼科受診を行い、
網膜症を予防することが重要である。
高齢者の難聴=感音性難聴が多く補聴器の効果は低い
補聴器の効果がある伝音性難聴と
感音系(内耳以降)の障害で補聴器の効果が
低い感音性難聴がある。高齢者の難聴は感音性難聴
が多いため補聴器の効果が低い。
しかし、他の手立ては今のところないので、
補聴器をよく調整して用いる。
無料講座やってます!!
ケアマネ無料めーる講座!!2018年完全対応!